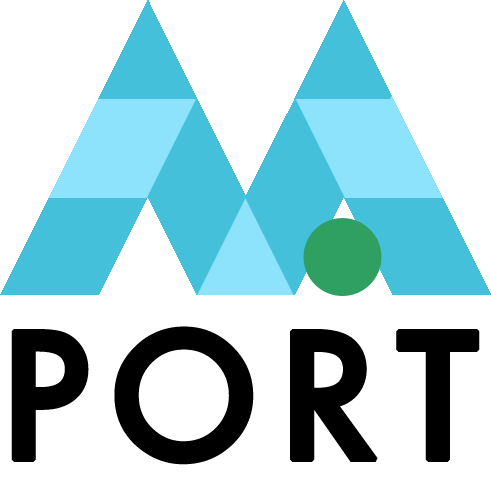事業譲渡の際、債権者の個別同意が必要?事業譲渡の実務を徹底解説!
2021.12.26 M&A知識事業譲渡は、株式譲渡と同じくらいM&Aの実務で利用されることの多いスキームです。今回は事業譲渡の実務において、債権者保護に主な焦点を当てて、実務上の留意点や事例を解説していきます。
事業譲渡とは
事業譲渡とは会社の経営権ではなく、事業や財産そのものを譲渡する行為です。事業を構成するする建物・土地などの資産の他、借入金や無形資産、従業員など様々なものを譲渡対象資産として含めることができます。買い手にとって事業譲渡の場合、簿外債務を引き継ぐリスクがない点がメリットの一つです。一方、事業を分割して譲渡する手法として、他には会社分割があります。会社分割と異なり、事業譲渡は、事業を承継させるための手法が、包括承認でなく、個別承認である点がデメリットになります。事業譲渡の対象となる債権、債務が多くなる場合、承継に異議を唱える相手が増える可能性があり、事業譲渡実現の可能性が低くなってしまいます。日本の中小企業のM&Aでも事業譲渡はよく使われますが、譲渡対象になる資産の一覧が多すぎると、譲渡実行までの期間が長くなってしまう点に注意しなければなりません。また、税務の面では事業譲渡の対象資産に課税対象資産が含まれている場合には、消費税が必要になる点は注意点の一つになります。
事業譲渡の必要手続
事業譲渡を実施する際、必要な手続は以下のとおりです。
- 事業譲渡契約書の締結
- 株主総会における事業譲渡契約書の承認
- 株式買取請求に関する株主への通知・公告
組織再編上の行為である合併や会社分割などと比べて、債権者保護手続や事前・事後の開示書類の備置は必要ない点が大きなポイントです。事業譲渡は取引行為であるため、いわゆる売買取引と性質が似ています。それでは1〜3の内容について、簡単に見ていきましょう。
1.事業譲渡契約書の締結
事業譲渡の最初のステップは事業譲渡契約書の締結です。事業譲渡契約書の概要は以下のような条項が挙げられます。
- 譲渡対象資産
- 譲渡期日、譲渡対価
- 譲渡対象となる権利義務の移転手続
- 競業避止義務
- 表明保証、補償、実行の前提条件、実行後の義務などM&A契約書における一般的な条項
事業譲渡契約書の締結自体は、取締役会決議など、自社の決裁ルールに基づいて意思決定することができます。通常のM&Aと同様に、基本合意書の締結、デューデリジェンス、契約交渉を経て、事業譲渡の意思決定を行います。
2.株主総会における事業譲渡契約書の承認
売り手の場合、事業譲渡の譲渡対象資産が総資産の5分の1を超える金額であれば、株主総会の特別決議による承認を受けなければなりません。承認を受ける期限は、譲渡実行日の前日までとなりますので、事業譲渡を実施する前に、株主総会の招集通知発送など、全体のスケジュール・時間を固めておく必要があります。
買い手の場合、事業全部の譲受である場合に限り、株主総会による特別決議が必要になります。また、売り手の場合と同様に、金額的に小さい案件であれば、事業全部の譲受であったとしても、株主総会の特別決議を省略させることができます。一部の事業譲受であれば、原則として株主総会決議が不要となるため、少数株主の議決権に影響することなく、事業譲受を進められる点が特徴です。
そのため、買い手であっても、売り手であっても、事業譲渡を行う際は、どのような機関決定が必要になるのか、弁護士や法律事務所の支援・サポートが必要なケースがあります。
3.株式買取請求に関する株主への通知・公告
少数株主の利益を保護することを理由に、事業譲渡に反対する株主は、株式買取請求権を有しており、自らの保有する株式を「公正な価格」で譲渡することを請求することができます。(会社法469条2項)
当時会社は、株式買取請求にかかる株主への通知または公告・催告を、事業譲渡の効力発生日の20日前までに行わなければなりません(会社法785条)。公告は官報などによって実施することが可能となります。
公正な価格は、株主と当時会社の中で交渉することになりますが、交渉決裂の場合には、裁判所に申し立て、裁判所が公正な価格を決定することとなります。
債権者の個別同意が必要な場合とは
合併(新設・吸収)や会社分割など組織再編上の行為を行う場合、会社法において、債権者保護手続が必要な旨が定められています。一方、事業譲渡の場合は取引行為であり、債権者保護手続は不要です。通常の売買取引と同じ取り扱いであるため、債権者に事業譲渡のことをその都度知らせる必要はありません。
事業譲渡の譲渡対象資産に、買掛金などの債務が含まれている場合、契約書に記載されている内容とは別に、先に債権者に個別同意を得ることが必要です。事業譲渡の場合、権利や契約を移転させるためには、事業譲渡契約書の締結だけでは足らず、個別に同意を得ていかなければなりません。
債権者の個別同意が得られない場合について
事業譲渡契約書を締結した後、債権者からの個別同意が得られない場合には、その個別の資産・負債は移転されないことになります。事業を進めるにあたり、重要な資産や契約が移転されなければビジネスを引き継ぐことができないといったケースでは、事業譲渡契約書において、当該資産等の移転を実行の前提条件として設定しておくといった対応が求められます。個別同意を得られなければ、事業譲渡契約書に記載されている内容が実行されないため、事業譲渡は実行されません。事業譲渡の場合、デューデリジェンスの過程で、どのように必要な資産・負債・契約等を引き継ぐか、引き継ぎのためにどのような資料を作成することが求められるのか等、詳細に調査しておくことが、事業譲渡を成功させるための重要なポイントです。
従業員の引き継ぎにも個別同意が必要
事業譲渡の場合、当該事業に従事している従業員も譲渡対象に含めることができます。しかし、その従業員が買い手企業への転籍を拒んだ場合には、労働契約を買い手企業が引き継ぐことはできません。そのまま事業譲渡する会社側に残り、他の事業などに従事することになります。事業譲渡の価値の源泉が、特定のキーパーソンに偏っている場合には、事業譲渡実行前に、特定のキーパーソンと事前によく話しておくことが求められます。会社の事業に従事している者であっても、事業譲渡の際は、基本的には自由に意思決定できると覚えておきましょう。従業員の引継ぎに際し、問題が発生する可能性が高い場合には、人事系のサービスや社労士の紹介を受けるなど、状況に応じて適切な専門家を活用するようにしましょう。
まとめ
以上のとおり、今回は事業譲渡の実務上の流れを簡単に解説の上、債権者・債務者の個別同意が必要なケースを見てきました。合併や会社分割などと異なり、法的な債権者保護手続は必要ありません。
他方で、事業譲渡の場合は、対象資産や契約の移転手続は、それぞれ個別に同意や承諾を得ていく必要がある点は留意が必要です。仮に同意や承諾が得られない場合には、事業譲渡の効果がないため、個別同意が得られるかどうかは事前に感触を確かめておく必要があります。
事業譲渡のスキームを実際に進めるためには、M&Aアドバイザリーや弁護士、税理士などのM&Aや組織再編行為に詳しく、ノウハウを持っている専門家に相談してみるのがおすすめです。法律に従い、適切な手続を漏らさずに把握しておくことが事業譲渡成功のための近道となります。