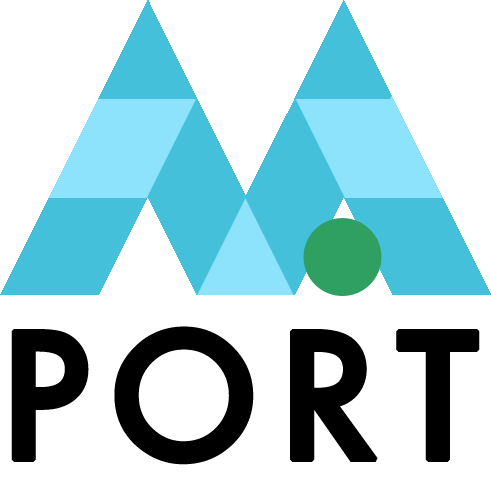M&Aの流れ【検討段階からの手続きを徹底解説】
2020.05.22 M&A知識M&Aの手法により多少の違いはあるものの、一般的なM&Aの手続きは「検討・準備」→「交渉」→「契約締結」という流れで進みます。
今回の記事では、M&Aの流れに関して検討段階から順番に解説します。
M&Aにおける検討・準備段階の流れ
M&Aの検討から準備までの流れは下記になります。
⑴M&A仲介・アドバイザリーへの相談・契約
当事者企業のみでM&Aの相手探しや実務を行うのは難しいため、買収企業と売却企業ともに、まずはM&Aをサポートする仲介会社やアドバイザリーを探します。
M&Aでは契約の締結や企業価値算定など、専門知識を要する実務が多々あります。
スムーズにM&Aを進めるためにも、かならず仲介会社やアドバイザリーにサポートしてもらうのがオススメです。
業者によって手数料の体系やサポートの範囲は異なるため、複数の業者を比較検討しましょう。
⑵売り手による各種提案資料の作成
次に、売り手企業が仲介業者の協力を得た上で、買い手に対して提示する提案資料を作成します。
具体的に事業内容や財務状況、自社の強みなどが分かる資料に加えて、抽象的に会社の情報を記した「ノンネームシート」も作成するのが一般的です。
なお買い手候補にM&Aを打診するに際しては、あらかじめ重要情報が記された資料を相手方に提示して良いかについて、仲介会社から確認を受けるので安心です。
⑶M&Aの候補企業の選定
作成した資料をもとに、仲介会社が売却先候補となる買い手企業を選定します。
まずは希望の売却価格や事業内容などの基本情報をもとに、20〜30社ほどの候補企業が載っているロングリストを作成します。
次に、その中からM&Aの実現可能性などを考慮して、実際にM&Aの打診を行う企業をまとめたショートリストを作成します。
M&Aにおける交渉段階の流れ
M&Aの相手候補が決まったら、本格的に相手企業と交渉を進める流れとなります。
⑴ノンネーム資料の提供と検討
M&Aのマッチングを行うにあたって、まず仲介会社は、買い手候補に売却側のノンネーム資料を提供します。
買収企業はノンネーム資料をもとに、本格的にM&Aの交渉を進めるかを判断します。
ノンネームシートには抽象的な情報しか記載されていないため、売り手企業の機密情報が不本意に漏洩するリスクはありません。
⑵ネームクリアと詳細情報の検討
買い手がノンネームシートに興味を示したら、売却企業はネームクリアを行います。
ネームクリアとは、売り手企業の社名や具体的な事業概要などを開示する手続きです。
この手続きが行われることで、買い手は本格的に売り手企業の強みや財務情報などを確認できるようになります。
ただし売却企業にとってネームクリアは、機密情報がもれるリスクを高める行為です。
そのため、秘密保持契約を締結した上でネームクリアが行われるケースが多いです。
⑶経営者同士の面談
売却側と買収側が互いにM&Aを進めたいと意思表示した場合、双方企業の経営者同士による面談を実施します。
基本的にこの面談は、M&A後の経営方針や従業員の取り扱いなど、数字面以外の観点を話し合う目的で行われます。
⑷意向表明書の提示と条件交渉
トップ面談を経たら、次に買い手が売り手に対して「意向表明書」を提示する流れになります。
意向表明書とは、買い手が希望するM&A手法や買収価格などが記載された書面です。
この書面を基に、M&Aの基本的な部分に関する条件交渉が行われます。
M&Aにおける契約段階の流れ
ある程度条件交渉を進めたら、本格的に契約を締結する流れへと入ります。
⑴基本合意書の締結
交渉により双方がM&Aの基本条件に合意したら、「基本合意書」を締結します。
基本合意書には買収価格やM&Aの手法、従業員の処遇など、これまでに合意した条件が記載されます。
また、他の候補先とM&Aの交渉を行わない旨を約束する「独占交渉権」が条件に付与されるケースも多いです。
⑵デューデリジェンス
基本合意書が締結されたら、買い手によるデューデリジェンスが行われる流れとなります。
デューデリジェンスとは、M&Aの潜在的なリスクを洗い出す目的で、売り手企業をあらゆる観点から精査する手続きです。
調査する分野は、「財務」や「税務」、「法務」、「IT」など多岐に渡ります。
買い手はデューデリジェンスの結果を基に、リスクを加味した買収価格の算定やリスクへの対処法、M&Aの実行可否などを判断します。
⑶最終条件の交渉
デューデリジェンスの結果を考慮した上で、M&Aの条件に関して最後の交渉を行います。
買収価格や従業員の処遇などはもちろん、経営者の処遇や買収代金の支払い方法など、M&Aの契約後の事柄に関しても調整を行います。
⑷取締役会や株主総会での承認(必要な場合)
M&Aの手法によっては、取締役会や株主総会での承認手続きが必要となります。
たとえば株式譲渡によるM&Aでは、ほとんどのケースで株式譲渡の可否について、取締役会または株主総会での承認が必要です。
⑸最終契約の締結
条件交渉やM&Aの承認などの手続きをすべて終えたら、いよいよ最終契約を締結します。
最終契約書には、M&Aに関して売り手と買い手が合意した内容(買収価格など)がすべて記載されます。
加えて、売り手がこれまで開示した情報に虚偽がない旨を示す「表明保証」や、表明保証に違反した場合に損害賠償請求が発生する旨を示す「補償条項」が盛り込まれることもあります。
⑹クロージング
M&Aの契約が締結されたら、最後にクロージングを行う流れとなります。
クロージングとは、会社や事業の引き渡しや代金の支払いなど、M&Aの効力を確かなものとするための手続き全体を意味します。
具体的には、株式や事業用資産、従業員や取引先との契約などが引き継がれます。
完全に事業・会社やそれに付随する資産が買い手に移行した段階で、M&Aの流れはすべて完了となります。
なお最終契約の締結からクロージングまでの間には、時間差が生じるケースが多いです。
時間差が生じる際には、その間に取引先や顧客に対してM&Aを実施すると良いでしょう。
M&Aの流れについてのまとめ
若干専門的な手続きが必要となるものの、M&Aの手続きは ビジネスで日頃行われている商取引と大きく変わりません。
専門的な業務や相手探しは仲介会社やアドバイザリーに任せることができるため、悩んでいる方もぜひM&Aにチャレンジしていただければと思います。