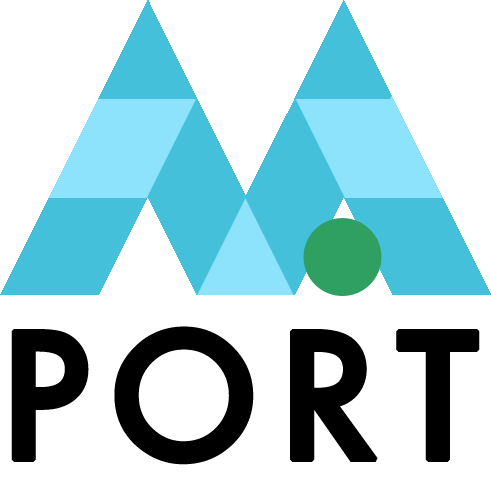あなたの飲食店はいくらで事業売却できる?相場感を解説!
2021.06.27 会社・事業を売る事業売却には、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割など様々な手法がありますが、飲食店の事業売却を考える際、まず考えるのはいくらで売却できるのかということです。
専門家に相談することで、大体の金額を教えてもらえることもできますが、自分で大体の相場感を持っておくことも大切です。
今回は、飲食店がいくらで売れるかについて、計算方法を具体な事例を用いて解説していきます。
事業売却金額の計算方法
事業売却金額の計算方法は、主に以下の4種類の方法があります。
- DCF法
- マルチプル法
- 修正純資産法
- 年買法
中小規模の事業売却案件で、簡易的に相場感を知りたい場合には、上記の中で年買法が使いやすい方法になります。
年買法は、「対象会社・事業の純資産+営業利益×3〜5年分」と計算されます。
3〜5年分の部分については、業種・業界・業態、それぞれの飲食店の評価により様々で、事業の成長性・安定性などによっては3年よりも短くなりますし、5年超の評価が付くこともあります。
ここでは相場感を知ることが目的であるため、3年を使って、具体的な数字を当てはめてみましょう。
居酒屋A店の事業売却金額
A店の財務状況は以下のとおりです。
- 売上高2,000万円、営業利益300万円
- 資産1,000万円、負債800万円、純資産200万円
年買法の計算式に当てはめた場合の事業売却金額は以下のとおりです。
- 事業売却金額=200万円+300万円×3年分=1,100万円
居酒屋A店の事業売却金額相場は、1,100万円と計算されましたので、この金額を交渉の目安にすることができます。
M&Aマッチングサイトなどでは、売り手の希望売却金額レンジが開示される場合がありますが、レンジ最大額以上の金額では基本的には売却できない点に留意が必要です。
交渉上、最初にテーブルに乗る金額は事業売却の最大値にアンカリングされます。
そのため、居酒屋A店を事業売却する際には、希望金額を1,000万円と1,100万円を下回る金額から交渉することはお勧めできません。
飲食店事業が成長している場合の事業売却金額を算定
飲食店事業が波に乗っており、年々成長している場合、事業売却金額の算定方法として、DCF法を採用することもできます。
DCF法とは、対象事業が生み出す将来キャッシュフローを現在価値に割引計算することで事業売却金額を算定する手法です。
具体的には、売り手が作成した飲食店事業の5年程度の事業計画書を元に計算していきます。
一方、飲食店事業の特徴として、「箱物ビジネス」である点が挙げられます。
飲食店の席数にはキャパシティがあり、1日の顧客数に限界があるため、自然に事業計画上の売上も成長の限界があります。
しかし、他店舗展開・FC展開やテイクアウト事業、EC事業、その他サービス業・手数料ビジネスなどを展開しており、多数の従業員を雇用しているような場合には、将来の成長を描くことができます。
1店舗だけの収益でなく、収益の柱が複数ある分には、よりアグレッシブな計画を策定でき、事業売却金額も高くできる可能性があります。
成長飲食店事業を営むB社の事業売却金額
B社は複数の飲食ブランドを保有しており、ラーメン店、カフェ、居酒屋など様々な種類の飲食店を運営しています。
B社の現状の営業利益(=営業キャッシュフローとします)は1,000万円で、来年以降も下記のとおり成長していくことが見込まれています。
- 2年目:2,000万円
- 3年目:3,000万円
- 4年目:4,000万円
- 5年目:5,000万円
5年目以降は、5,000万円の営業利益が継続すると仮定した場合、B社の事業売却金額を算出してみましょう。
DCF法を使用するにあたり割引率は10%、法人税率は30%とします。
2年目の営業利益2,000万円の現在価値は、下記のように計算することができます。
- 2,000万円×(1-30%)×1 / (1+10%)=1,272万円(①)
3年目の営業利益3,000万円の現在価値は以下のとおりです。
- 3,000万円×(1-30%)×1/(1+10%)^2 = 1,736万円(②)
4年目、5年目も同様に計算すると、4年目は2,104万円(③)、5年目は2,390万円(④)と計算されます。
5年目以降の価値を継続価値と呼びますが、継続価値は以下の計算式で計算されます。
- 5,000万円÷割引率10% = 5億円
5年後の継続価値が5億円ということですので、現在価値に計算し直すと以下のようになります。
- 5億円×1 / (1+10%)^4 = 2億3,905万円(⑤)
上記の①〜⑤の計算結果を全て合計したものがDCF法で計算された事業売却金額となります。
- ①〜⑤の合計=3億1,407万円
業績が低迷している場合
業績が低迷しており、廃業寸前の飲食店であっても事業売却が可能な場合があります。
営業利益や将来キャッシュフローが赤字であれば、上記で計算してきた年買法やDCF法では評価額(バリュエーション)がマイナスとなってしまいます。
そのため、基本的には価値が付かず、買い手を探すことは困難な状況です。
ただし、土地や建物を売り手が保有している場合には、不動産の価値を見込んで事業売却できるケースがあります。
土地建物付きの飲食店C社の事業売却金額
C社は地方でイタリアンレストランを経営していますが、新型コロナウィルスの影響もあり、業績は低迷しています。
土地と建物の所有権は売り手が持っており、今回の事業売却では、土地と建物も含めての売却を考えています。
C社の財務状況は以下のとおりです。
- 売上高500万円、営業利益▲200万円
- 土地・建物の時価は5,000万円を見込む
このケースでは、事業の価値としては0円と評価されたとしても、土地・建物の価値として5,000万円以上で売却できる可能性があります。
買収後に経営再建できる買い手であれば、事業価値を0円超で評価してくれる買い手候補が現れ、より高い価格で成約できるかもしれません。
買い手目線での注意点
買い手は飲食店を買収することで、ゼロから新規出店するよりも早くビジネスを開始することができる点が大きなメリットです。
居抜き物件を賃貸して開業する場合と比べても、M&Aであれば、固定の顧客がいる、料理人などの人材をそのまま引き継ぐことができるなど、有利な点が数多くあります。
一方、対象事業の物件、設備、内装などが古ければ、改修コストがかかることもある点は留意が必要です。
買収金額に加え、必要に応じて店舗の改修費、M&A仲介会社やFAへの仲介手数料、公認会計士・税理士・弁護士など専門家へのデューデリジェンス費用、契約書レビュー費用など全ての費用を網羅的に洗い出し、投資金額が回収できるかを検討する必要があります。
まとめ
以上、飲食店の事業売却において、相場感を簡易的に計算する方法を解説してきました。
事業価値の計算方法は、様々ありますが、飲食店の置かれている状況に応じて使い分ける必要があります。
また、あくまでも簡易的な計算方法である点は留意が必要で、実際のM&Aの相場とは異なる場合もあります。
より詳しく相場感を知りたい場合には、M&A仲介会社やFAに相談することが最も効果的で安心できる方法です。
各社はそれぞれもっている計算ロジックで事業価値をレンジで算定してもらえる他、実際のM&A事例に照らした相場感も持ち合わせています。
自分の経営している飲食店の価値を知った上で、事業売却のプロセスを進めることもできます。
事業売却する気はなく、価値を知りたいだけでも相談に乗ってくれることもあるので、気軽にM&A専門家に相談してみることがおすすめです。